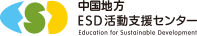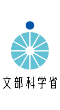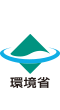昨日 10 月 23 日(木)、山梨県の甲府地方気象台は富士山の初冠雪を発表しました。平年より21日遅く、昨年より15日早い観測です。
富士山の初冠雪の平年値は 10 月 2 日ですので、平年より21日遅くなりました。また昨年の2024年は、観測開始の1894年(明治27年)以来、観測史上、最も遅い 11 月 7 日でした。
2013年に世界文化遺産に登録された富士山ですが、近年、さまざまな問題が出ています。その問題は私たち一人ひとりの行動とも関わっています。富士山の問題をとおして、私たちはこれからどんな行動を選んでいくとよいでしょうか?
◆ごみ問題
登山道や周辺には、ペットボトル、お菓子の包み紙、タバコの吸い殻など、さまざまな種類のごみが散乱。とくに、登山シーズンにはごみの量が増え、自然環境を大きく壊してしまう原因となっています。また、野生動物がごみを食べて中毒を起こしたり、雨によって流れ出た有害物質が土や水を汚染したりする可能性があります。
◆シカの食害
富士山のまわりでは、たくさんのニホンジカが暮らしています。そのシカによる食害が出ています。シカが木の皮や若い芽、草をたくさん食べてしまうことで、森に大きな影響が出ています。シカが食べすぎると、若い木が育たず森が再生しにくくなります。さらに、ツノをこすりつけてツノ研ぎをする習性があるため、木の皮を傷つけてしまい木が枯れてしまうことも起こっています。。木々が減ると、土が流れやすくなり土砂災害のリスクも高まります。
また、シカが植物を食べ尽くしてしまうことで、それを食べていた昆虫や鳥がすめなくなり、森の生きものたちのバランスがくずれてしまうのです。
~なぜシカは増えている?~
明治から戦中くらいにかけて野生動物が乱獲されて、シカも戦後すぐくらいまでは絶滅寸前だった。そのため保護政策がとられて、1948年にメスジカの狩猟が禁止になった。(2007年に解禁)
また、天敵のニホンオオカミが絶滅して捕食者がいないことや、地球温暖化で豪雪が減り、冬でもエサを確保しやすくなった。
※ニホンオオカミは森林破壊による生息地の減少、人間による乱獲、伝染病、様々な要因で絶滅しました。(参考:ニホンオオカミ絶滅の理由と影響について)
◆森林限界の上昇
森林限界とは、木が育つことができるぎりぎりの標高のことです。地球温暖化で気温が上がると、これまで木が育たなかった標高の高い所にも木が生えてくるようになります。富士山でも、森林限界が少しずつ山頂のほうに上がってきていることがわかっています。
この変化は、高山植物のすみかを狭めたり、山の生きものたちのくらしを変えたりして、富士山本来の自然環境に大きな影響を与える可能性があります。
◆永久凍土の減少
永久凍土とは、地面の中が2年以上ずっと氷のように凍っている土や岩のことです。この氷が溶けると、山が崩れやすくなり、土砂崩れや土石流が増えたりする心配があります。また、高山植物の育つ環境が変化し、生態系に影響を与える可能性もあります。
◆湧水地の減少や水質悪化
富士山の麓には豊かな湧水地が点在しています。しかし、近年、これらの湧水地は湧水量の減少と水質の悪化が心配されています。湧水量の減少は、森林伐採や開発、気候変動による降水量の減少などが原因とされています。
水質の悪化は、生活排水や農薬などの流出のほか、登山者によるごみの不法投棄やポイ捨てなどが主な原因と考えられています。
<参考>
◆地球温暖化で富士山の姿が変わる?懸念される影響とは(デコ活)
https://ondankataisaku.env.go.jp/decokatsu/weather/article05.html
◆富士山の環境問題の現状とは?美しい自然を守るための対策や取り組み事例(ELEMINIST)
https://eleminist.com/article/3853
◆世界の山々を登った私が感じる富士山の「異常事態」(アルピニスト・野口健)